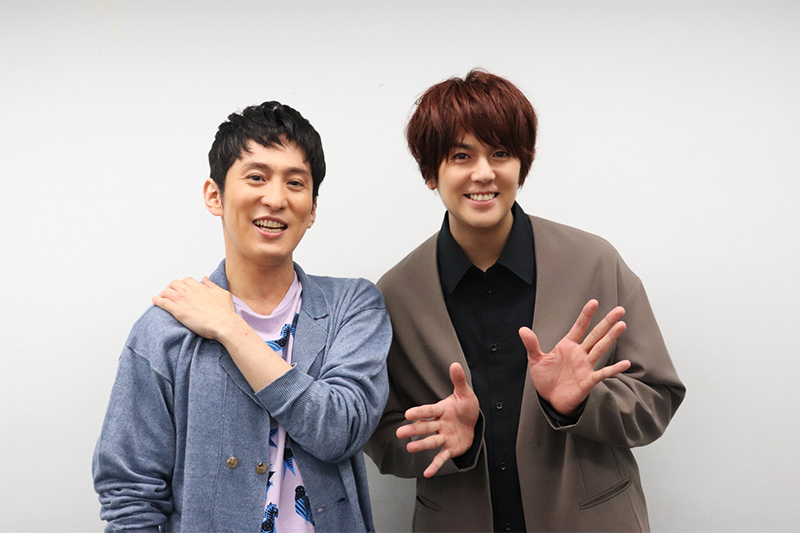INTERVIEW
成河さん(左)、浦井健治さん(右)
── 今回、お二人は交互に「ぼく」と「大切な人たち」を演じるとのこと。浦井さんが「ぼく」を演じる回は成河さんが「大切な人たち」、成河さんが「ぼく」を演じる回は浦井さんが「大切な人たち」を演じますが、ダブルキャストと言っていいんでしょうか?
成河 ダブルキャストじゃないんじゃないかな。ダブルチーム?
浦井 役替わりですね。
── お二人とも様々な場所でご活躍ですが、共演自体は久しぶりですね。
浦井 はい。共演したのは『THE BIG FELLAH ビッグ・フェラー』('14年)一作だけなんですが、濃い作品でしたし、森新太郎さんの演出にたくさん揉まれ、ともに励まし合って乗り越えた経験があるのでとても信頼しています。そもそも僕は、共演前から成河という役者に惚れていたんです。村井國夫さんをはじめ諸先輩方から「すごいのがいるよ」と聞いていて、僕自身も『春琴』『夏の夜の夢』などを観て「とんでもないな」と思っていた。同世代の中で飛びぬけてすごい人。でもいざ共演してみたらお茶目なところはあるし、フレンドリー。そのギャップ萌えにもやられました(笑)。
成河 そうだね、『ビッグ・フェラー』が初共演だった。僕は自分はどこにでも生える雑草だと思っています。そうありたいと思い、色々な仕事をし始めて、ミュージカルを主戦場にしている同世代とも会い出していた時期でした。健ちゃんは僕とは違う出自を持ち、すごく独特な思考回路と表現方法を持っているな、面白いなと思って、裏で色々と手をまわし、情報を得ていました(笑)。僕、同世代を大事にしているんです。同世代がどんなことをやって、どんなことを考えているのかを知りたい。中でも健治クンは、変なヤツでしたね~。
浦井 大丈夫なのかなこいつ、って(笑)?
成河 いやいや、そういう不安さじゃなくて。出自が、一般的な大きなマーケットとしてのミュージカルということでもないでしょ? 仮面ライダーだし(※浦井のデビューは『仮面ライダークウガ』'00年)。
浦井 敵のボス役だったし、仮面ライダーじゃないよ。
成河 そっかそっか。
浦井 成河も、本当にやってきたことが僕とは全然違う。身体能力も演技力のすごさも、僕とは違うところから出てきている。一緒にやっていて色々と面白いです。
成河 そういう意味では今回のキャスト4人、出自が本当にバラバラ。濱田めぐみさんは劇団四季で、柚希礼音さんは宝塚歌劇団ですから。
浦井 メー。
成河 ……わからない。
浦井 ひつじ。
成河 ひつじか(笑)。出自な。
── (笑)。共演の濱田めぐみさん、柚希礼音さんの印象は。
浦井 僕は柚希さんとは初共演。先入観がないからこそ、母親と「ぼく」として新鮮にできるんじゃないかな。あと年齢が近いので、友人などには「柚希さんが母親役? 恋人じゃなくて?」と言われたりもしました。ある種、母性を超越した愛のカタチなども見えてくるかもしれないと思っています。濱田さんは何度も共演していて、大先輩ですが非常にフレンドリー。僕も「めぐ」と呼ばせてもらっていますし、「そうしてよ」という空気で接してくれる方。今回も楽しみにしています。
成河 僕も柚希さんは初めましてです。めぐみさんは昨年の『イリュージョニスト』が初共演でした。コロナ禍だということもありとても大変な環境での創作で、めぐみさんとは「あれをやり切ったんだから、なんでもできるよね」と話しました。戦友感がありますね。

── 本作は、交通事故で記憶だけでなく、「眠い」「お腹がすいた」といった感覚すら忘れてしまった草木染作家・坪倉優介さんが体験した実話をベースにしたもの。この物語をどう受け止めていますか?
浦井 坪倉さんの経験は、辛く衝撃的な出来事だと思う。今回は、戻らない記憶というものに向き合い、新しい記憶を作っていく、それが“COLOR”になるというところに焦点が当たると思うのですが……簡単に「こうですよね」と言える軽いものではなない。ましてや、今もご活躍されている方ですから。演劇として扱うには、ヒリヒリとせざるを得ない。これをどうお客さまに伝えるのか、責任を持って向き合わないといけないと思っています。ただ、彼を支えたお母さまの心を思うと、演じる側が泣いてはいけないのですが、どうしても涙が出てきてしまいます。
成河 難しいよね。僕が坪倉さんのエッセイを読んだ時から感じていたのは、彼が「お腹がすいている」という感覚すらわからないとなった時に、我々は「辛いだろうな」と思う。でもその時の彼は、そのことを辛いと思っていたのだろうかということなんです。僕たちが「3食きちんと食べないと」と思っている社会が、「3食食べないと辛いだろう」「今は眠いだろう」と彼に迫ることが、彼は辛かったのではないかと。つまり、この話を演劇にするにあたり、僕たちが今、当たり前だと思っている社会に彼が適応しようとしていくところのズレと軋轢、それでもその社会に乗っかっていった過程を提示することが、この物語から見出す意味なんじゃないかと思うんです。
浦井 うん。
成河 彼が辛かったんだとか、可哀想だとか、それを乗り越えてとても偉い、という話になったらとてもよろしくない。でも、簡単にそうなり得る物語。しかも演劇はある程度、視点をお客さんに強制してしまう芸術です。今、そうならないようにみんなで頑張っているところで、そういう試行錯誤ができるのも、新作の醍醐味ですね。僕としては、彼がたどった道は正解かも不正解かもわからないという距離感の中で、「我々が当たり前に過ごしているこの社会が、果たしてすべて正しいのか」というところにたどり着けたらいいなと考えています。
──演劇として届ける意義といったところに話が及んできました。キャストが「ぼく」「母」「大切な人たち」の3人だけというのは演劇的だと思うのですが、特に「大切な人たち」がどんなポジションになるのか含め、教えていただけますか。
浦井 先日初めて4人揃ってリーディングをやったのですが、そこからまた作り直し(笑)。みんなで『COLOR』を作ろうと頑張っているところです。
成河 新作を一から作るってとても大変なこと。今、新作を実話から立ち上げていくという過程の渦中にいます。キャストは「ぼく」「母」「大切な人たち」の3人だけなのですが、この「大切な人たち」というポジションの俳優は、劇中で色々な役を担う。ここがとても重要になってきます。要するに、実話を実話として淡々としゃべるだけだと演劇にする必要がない。「ぼく」と「母」が主人公の話だと、ドラマでやった方がいい。実話を演劇にした時に、“第三者の語り手の視点で描く”ことが構造として必要になってきます。
浦井 そのことで、物語とお客さまの橋渡しをするわけです。
成河 そう。よく言われることですが(ドラマや映画などとは違い)「演劇は三人称」ということ。主観的に話していたら、どんどんセンチメンタルになっていっちゃう。そういう意味で「大切な人たち」という役柄が非常に重要になってくると思います。どういう形が一番ふさわしいのか、今みんなで模索しています。大変です。
浦井 実際、坪倉さんご本人は今も講演会で体験を語ったりされていますが、彼を取り巻くまわりの人たちの体験を、お母さまを通して聞いていた方がいらっしゃるんです。その方がもしかしたら、お客さまに一番大切なものを伝えやすいポジションかもしれません。この作品を観た方に何かしらの希望を持って帰っていただけるような、そういうところに繋げる第三者の役割。しかもそれを、成河と僕で役を入れ替えてお届けすることで、見えてくる景色も変わってくるし、より深くお届けできると思う。役を替えてみたらまったく違う作品を観た感覚になるかもしれない。
成河 上演に向けて何年も準備していたプロデューサーをはじめ、大切に大切に届けたいとみんな思っているし、演劇にする意義を最後まであきらめずに作っていきたいよね。しかも我々俳優も、台本作りに能動的に関われるような環境を作ってくださっていますので。今は“語り口”をどう作っていくかでみんなで試行錯誤しているところ。そして健ちゃんが言ったように、「ぼく」をやる回/やらない回、ではなく、この4人でひとつのチームとして、坪倉さんのストーリーを語っていく、最終的にはそういう形に持っていきたいなと思っています。

──それが、冒頭で「ダブルキャストではない」とおっしゃったところに繋がるんですね。お二人がふたつのポジションをスイッチして演じる、あるいは濱田さんと柚希さんの二人が「母」を演じる、観客は両方観ることができて楽しい……というだけでなく、お二人が両面から作っていくこのシステム込みで、この作品が成り立っていると。
成河 そう思います。我々はそのクリエイションをどう楽しむか、というところ。あんまりそう見えないかもしれないけれど、これはちょっと“普通じゃない作品”なんですよ。既存のものに当てはめて語れない。今までやったことのないことを、やろうとしています。
浦井 うん。やったことがないし、お客さまにとっても、きっと2パターン観たら毛色すら異なっているように見えると思うし、でもそのことでこの物語の核を持って帰っていただける気がします。子どもが砂遊びするみたいに、掘り出して「あ、見つけた!」というような体験をお客さまが脳内でやっていただけるんじゃないかな。この時代だからこその大切なものを感じ取ってもらえるものになるんじゃないかなと思います。一筋縄ではないかないし、簡単なことではありませんが。
成河 ダブルキャストではないとはいえ、2タイプの作品が出来上がる。坪倉さんの半生を、ふたつの面から見ることができます。さらに今回特殊なのが、僕と健ちゃんが、その両面に関われるということ。それはすごく楽しい。一般的なダブルキャストのシステムだと、自分が関わる面だけを一生懸命作ってもう一方は関われませんが、今回はそうではありません。お客さまにとっても、どちらの面が正しいかではなく、多面的な視点で見る楽しさを感じていただけると思います。
──音楽についてもお伺いします。「トイレの神様」で有名な植村花菜さんが初めてミュージカルの楽曲を書き下ろされますが、どんな音楽ですか?
成河 弾き語り系の、シンプルだからこそ豊かな楽曲です。
浦井 聴いていると涙が出てくる。素晴らしい音楽だよね。
成河 いわゆる西洋由来のミュージカルの手法とは真逆のタイプの楽曲ですので、それが吉と出るか凶と出るかという面白さで僕はゾクゾクしました。J-POP的な弾き語りの音楽でドラマを紡ぐって、なかなかのチャレンジだと思うんです。日本のオリジナルミュージカルはけっこう、音楽との融合で躓くことが多かったから。シンプルに紡いでいくとどうなるか、これは、将来のミュージカルの作り手たちにも見てもらいたいな。
──最後にお客さまにメッセージをお願いします。
浦井 坪倉さんの経験は、誰にでも起こりうる出来事です。彼は過去を失い、そこから出会った人から感じたこと、母親とともに歩んだ経験から得た大切なものを語っている。このコロナ禍の時代でも、希望を持って前に進んでいけるような気持ちを感じてほしいとプロデューサーは言っています。ただ、それだけではない醍醐味もあると思う。ある種時代への風刺や問題提起という見え方もするかもしれない。人によって見え方が異なる、そんな作品にしていけたらと思います。
成河 演劇は自分たちの社会について考える場所だと思っています。この話は記憶喪失について考える場所ではなく、自分たちの社会が坪倉さんに与えた影響を考える場。それを僕たちは稽古場でずっと考えるし、お客さまも客席で考えざるを得ないと思う。僕たちが、自分たちの日常や社会を見直したり、問い直したりする、よい機会になると思うので、ぜひいらしてください。
(取材・文・撮影:平野祥恵)
<衣装協力>
浦井健治
REV(Blue IN Green PR TEL:03-6434-9929)
<スタッフ>
ヘアメイク・タナベ コウタ
スタイリスト・吉田ナオキ(浦井健治)